「イグノーベル賞」という賞を、一度はテレビなどで見たことがある人は多いと思います。一風変わった研究が受賞している、というイメージが強いかもしれません。
実際はどのような研究が受賞しているのでしょうか?
今回の記事では、イグノーベル賞について概要を解説しつつ、これまでの受賞例についてもいくつか解説します。
なお、2023年のイグノーベル賞授賞式は9月14日にWeb開催されます。
この記事がイグノーベル賞への理解の一助になれば幸いです。
ノーベル賞とは
イグノーベル賞の解説にあたり、はじめにノーベル賞について簡単にご紹介します。
イグノーベル賞のもとになったノーベル賞はダイナマイトの発明で知られるアルフレッド・ノーベルの遺言に従って創られた賞です。化学、物理学、医学生理学、文学、経済学、平和の5つの部門からなり、世界で最も権威ある賞のひとつです。
イグノーベル賞とは
イグノーベル賞とは、一言でいうと「人々を笑わせ、そして考えさせる業績」に対して贈られる賞です。
「イグノーベル(Ig Nobel)」という名前は、ノーベル賞の創設者であるアルフレッド・ノーベルの姓に否定的な接頭辞「Ig」をつけた造語で、「下等な、下品な、見下げた」という意味の「ignoble」を掛けたジョークになっています。
もっとも、最高権威と言っても過言ではないノーベル賞と比較しての自虐的な表現であって、優劣を示しているものではありません。これまでに受賞しているのは興味深く考えさせられる研究ばかりです。
イグノーベル賞は、1991年にイスラエルの科学関係雑誌『The Journal of Irreproducible Results(再現不能な結果ジャーナル)』の編集者 マーク・エイブラハムズ 氏によって創設されました。彼のエッセイ記事において「イグ」の意味するところについても論じられています。
なお、ロシア生まれのオランダ人物理学者であるアンドレ・ガイム博士は2000年に「カエルの磁気浮上」でイグ・ノーベル賞を受賞し、2010年には「炭素新素材グラフェンに関する革新的実験」でノーベル物理学賞を受賞しています。このようにノーベル賞、イグノーベル賞両方を受賞している例は2023年現在ただ一人となっています。
参考: Marc Abrahams(1999-10-01)「What Is This Ig?」Improbable Research
イグノーベル賞は毎年10組に贈られる
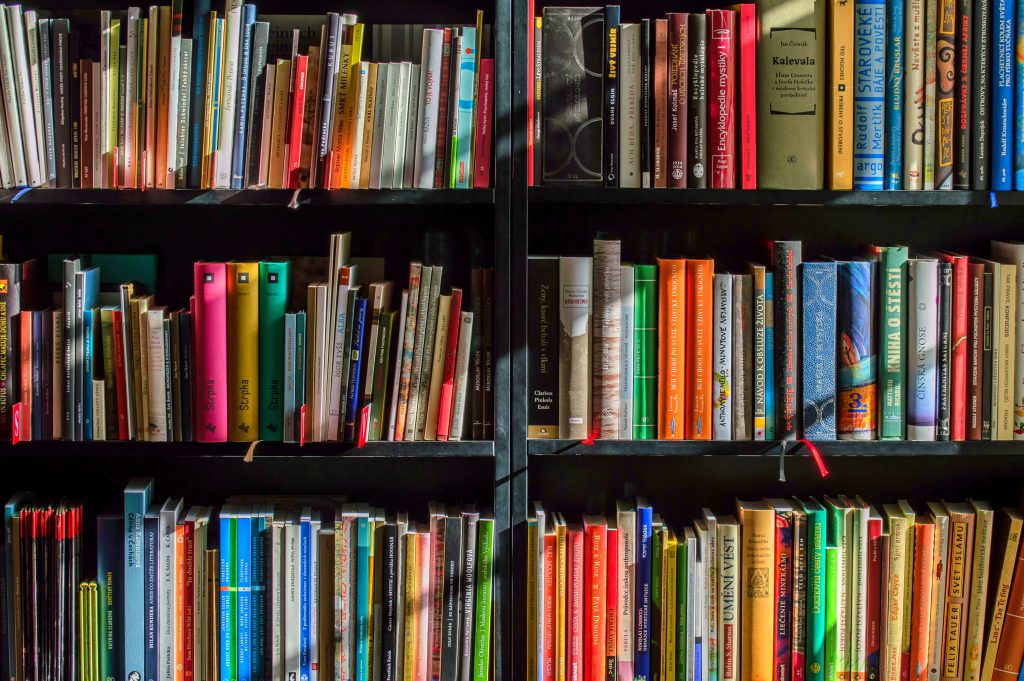
イグノーベル賞はノーベル賞と同じ化学、平和、物理学、医学生理学、文学、経済学といった部門のほかに、公衆衛生学、昆虫学、心理学などノーベル賞にはない部門も随時追加されています。
非常にユーモアあふれる研究が多い一方で、水爆の発明者であるエドワード・テラーが「一般とはまったく違った意味を『平和』に与えた業績を称えて」91年度のイグノーベル平和賞を授与された、といった強烈な皮肉が受賞理由に含まれている場合もあります。
イグノーベル賞の選考と授賞式
イグノーベル賞は受賞する研究のユニークさだけでなくユーモアと笑いにあふれた授賞式も大きな特徴の一つです。
ここからは選考と授賞式の内容について解説します。
選考
イグノーベル賞の選考委員会は一般からの推薦を受け付けており、毎年9000人に対する推薦が届くようです。推薦された候補者たちは前年までの候補者リストに追加され、その中から何段階かの選考委員会を経て受賞者が選定されます。「人々を笑わせ、そして考えさせてくれる研究」に合致する内容から毎年9月または10月に10名の個人または団体に授与されます。
参考: Improbable Research「Ig Nobel Nominations」(参照: 2023-07-31)
ユニークな授賞式
新型コロナウイルスの感染が拡大する以前は米国のハーバード大学にて授賞式が行われ、ノーベル賞受賞者も「プレゼンター」として登壇していました。
また、受賞者の旅費や滞在費は自己負担で、受賞講演では聴衆から笑いをとることが求められます。
受賞者たちは1本の長いロープ紐を握って一列になって壇上に上がります。
これは幼稚園のお散歩のパロディになっているようです。
また、研究を発表する場面では制限時間が60秒と定められています。
制限時間が過ぎると、Miss Sweetie Poo(ミス・スウィーティー・プー)と呼ばれる進行役の8歳の少女が登場し「もうやめて、私は退屈なの(Please stop. I’m bored.)」と連呼し、発表が強制的に終了となります。
聴衆は授賞式の初めに全員が紙飛行機を作り、投げ続けるのが慣例となっています。
そして、その掃除のためのモップ係は、ハーバード大学教授のロイ・グラウバーが例年務めています。
賞金は基本的にはありませんが、2015年から2017年は受賞者に10兆ジンバブエドルが授与されました。なお、この時点でジンバブエドルに貨幣としての価値はありませんでした。また、それぞれの業績に関係した副賞が授与されるようです。
固いイメージのある研究の世界ですが、一大発見をした研究者がこのようなコミカルな振る舞いをしている様子を見ると、研究に対するイメージも大きく変わりそうです。
ちなみに、2020年度から2022年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により授賞式はオンラインで行われました。
2022年度の受賞者を紹介
それでは具体的にどのような研究が受賞しているのでしょうか。
ここでは最新の2022年度の受賞者をいくつか紹介したいと思います。
Applied Cardiology Prize(応用心臓病学賞)
Applied Cardiology Prize(応用心臓病学賞)は「seeking and finding evidence that when new romantic partners meet for the first time, and feel attracted to each other, their heart rates synchronize」(あるカップルが出会い、お互いに魅力を感じたとき、心拍数が同期すること発見したこと)に対してチェコの研究者らに贈られました。
初対面の男女が体にどのような変化を示すか観察したところ、相手を魅力的に感じているかどうかはアイコンタクトやボディランゲージ、表情、汗などには現れず、心拍数が同期するかどうかによって判別することができるというものです。「ドキッとする」、「キュンとする」などと言われるような現象を科学的に実証した功績です。
参考: E. Prochazkova, E. Sjak-Shie, F. Behrens, D. Lindh, M. E. Kret (2021) 「Physiological synchrony is associated with attraction in a blind date setting」Nat Hum Behav 6, 269–278.
Literature Prize(文学賞)
Literature Prize(文学賞)はカナダの研究者らによる「analyzing what makes legal documents unnecessarily difficult to understand」(法的文書の理解を不必要に難しくしている原因の分析)に対して贈られました。法的文書が他の種類の文書と比較してどのような特徴を持っているか、被験者による理解度にどのような違いがみられるか調べた研究です。
参考: Eric Martínez, Francis Mollica, Edward Gibson (2022)「Poor Writing, Not Specialized Concepts, Drives Processing Difficulty in Legal Language」 Cognition, vol. 224, 105070.
Biology Prize(生物学賞)
Biology Prize(生物学賞)はブラジルの研究者らによる研究「whether and how constipation affects the mating prospects of scorpions」(便秘がサソリの交尾の可能性に影響を与えるかどうか、またどのように影響するか)といったものでした。
Solimary García-Hernández and Glauco Machado (2021)「Short- and Long-Term Effects of an Extreme Case of Autotomy: Does ‘Tail’ Loss and Subsequent Constipation Decrease the Locomotor Performance of Male and Female Scorpions?」Integrative Zoology.
Medicine Prize(薬学賞)
Medicine Prize(薬学賞)はポーランドの研究者らによる研究「showing that when patients undergo some forms of toxic chemotherapy, they suffer fewer harmful side effects when ice cream replaces one traditional component of the procedure」(有害な化学療法を受ける場合、その処置の伝統的な要素の1つをアイスクリームに置き換えると、有害な副作用が軽減されること)に対して贈られました。
メルフェランという物質を投与する化学療法において口腔粘膜炎を発症することがあり、それを抑えるために冷却療法が行われるそうです。この研究は冷却療法としてアイスクリームを「投与」し、その効果を示したという功績です。
Marcin Jasiński, Martyna Maciejewska, Anna Brodziak, Michał Górka, Kamila Skwierawska, Wiesław W. Jędrzejczak, Agnieszka Tomaszewska, Grzegorz W. Basak, and Emilian Snarski (2021)「Ice-Cream Used as Cryotherapy During High-Dose Melphalan Conditioning Reduces Oral Mucositis After Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation」Scientific Reports, vol. 11, no. 22507.
Engineering Prize(工学賞)
Engineering Prize(工学賞)は日本人に贈られました。受賞したのは千葉工業大学の松崎元教授などの研究チームです。対象となったのは「円柱形のつまみの回転操作における指の使用状況について」という論文における成果です。
この研究では、ペットボトルのキャップやオーディオの音量をあげるつまみなど、ものをつまんで回すとき、どのように指を使うのか、つまみの太さを変えて調べる実験を行い、つまみの太さと使う指の本数との関係や指の位置との関係を詳細に分析しました。
受賞理由は「人間がつまみを回すときに最も効率的な指の使い方を発見した」といったものでした。
参考: 松崎 元,大内 一雄,上原 勝,上野 義雪,井村 五郎(1999)「円柱形のつまみの回転操作における指の使用状況について」デザイン学研究,45巻,5号 69-76.
Physics Prize(物理学賞)
Physics Prize(物理学賞)は中国の研究者らによる「trying to understand how ducklings manage to swim in formation」(アヒルの子がどのようにして編隊を組んで泳ぐのかを理解しようとしたこと)に対して贈られました。
アヒルやカモの子たちが隊列を組むようにして母親の後を追う様子がみられますが、なぜ隊列を組むのか、どのような隊列を組むのが効率的なのか、それぞれの個体がどの程度のエネルギーを節約できるのかを調べたそうです。波の抵抗を計算し、こうした水鳥たちが組む隊形がエネルギー的に効率的な水泳であることを示しました。
参考: Frank E. Fish (1994)「Energy Conservation by Formation Swimming: Metabolic Evidence from Ducklings」Mechanics and Physiology of Animal Swimming, 193-204.
参考: Zhi-Ming Yuan, Minglu Chen, Laibing Jia, Chunyan Ji, and Atilla Incecik (2021)「Wave-Riding and Wave-Passing by Ducklings in Formation Swimming」 Journal of Fluid Mechanics, vol. 928, no. R2.
参考: IMPROBABLE RESEARCH 「Past Ig Winners 」(2023-07-31参照)
日本人は16年連続で受賞している

イグノーベル賞は日本人の受賞者が多く、1992年に資生堂の研究チームが「足のにおいの原因物質の特定」という研究で医学賞を初めて受賞しました。
そして、2007年以来日本人はなんと16年連続で受賞しています。
ここからは、日本人が受賞した例をいくつか紹介します。
実用化につながる研究も多い
「イグノーベル賞の研究は一見すると役に立たない」というイメージを持つ人もいるかもしれません。
しかし、実際にはイグノーベル賞を受賞した研究が商品となって社会に貢献しているケースもたくさんあります。
例えば、日本人のチームが開発したわさび警報器(2011年化学賞)や涙の出ない玉ねぎ(2013年化学賞)は商品化されています。
参考:REUTERS「イグ・ノーベル賞、「わさび火災警報器」で日本人7人受賞」
参考:ハウス食品株式会社「玉ねぎ研究でのイグノーベル賞受賞について」
カラオケ (2004年)
2004年、カラオケを考案した井上大祐氏が「お互いの曲をじっと聞くような、忍耐強さを鍛える新しい方法を編み出した」として平和賞を受賞しました。
なお井上氏は、世界で初めてカラオケを考案したわけではなく、ビジネス化に成功した人物であると言われています。
たまごっち (1997年)
1997年、たまごっちの開発者が「膨大な労働時間をバーチャルペットの飼育時間に費やさせた」として経済学賞を受賞しました。
初代たまごっちは1996年に発売され大ヒットしましたが、当時では珍しい飼育ゲームであったことから、少し皮肉的な意味があったのかもしれません。
日本人とイギリス人に受賞者が多い
イグノーベル賞は日本人とイギリス人が受賞者の常連となっています。
例えばこれまでに「映画『スターウォーズ』をみたバッタは興奮するか」という研究でイギリス人研究者が平和賞を受賞しました。
日本人やイギリス人に受賞者が多い理由として、イグノーベル賞創始者のマーク・エイブラムズ氏は以下のように述べています。
世界の大半の国では、変わった行動をすることは悪いことと思われます。そういう評判がついてしまうと、罰せられることだってあります。しかし、日本とイギリスは伝統的に違う。
日本には変わった人が多いです。変わった人が1人いると隣近所は快く思わないかもしれない。でも、他の皆さんはそれを誇りに思うんです。『変わった人は、我々みんなの変わった人だ』と。
だから、日本とイギリスでは、長い発明をしてこられたと思うんです。素晴らしいクレイジーに見えるものを壊さずに生かし、重宝してきたんです」
FNNプライムオンライン「日本には変人が多い!」 イグ・ノーベル賞の創設者が見たニッポン人
このような型にはまらない研究が大きなイノベーションを起こすこともあるといえます。
歴代の受賞テーマにはユニークな研究が多い
日本人以外の受賞でも面白い研究がたくさんイグノーベル賞を受賞しています。
以下のリンクは英語版ではありますが、これまでの受賞者とそのテーマが記載されています。
これまでにどのような研究が受賞しているのか調べてみるのも面白いかもしれません。
参考:IMPROBABLE RESEARCH 「Past Ig Winners 」
まとめ
今回はイグノーベル賞についてその概要や受賞例をご紹介しました。
「笑えて、考えさせられる」という選考基準を通して、イグノーベル賞は多くの人にとって難しく関係が薄いと考えられがちな「研究」や「科学」を身近なものにしていると言えます。また、最高峰とも言えるノーベル賞と比べると身近な学術誌に掲載された論文からも多くの受賞者が出ていることに気付いた人もいるかもしれません。
ノーベル賞を受賞するような偉大な研究も重要ですが、身の回りの素朴な疑問を学術誌に論文として発表する研究成果に結び付けられることは研究者としての力量に他なりません。イグノーベル賞は一般の人が科学に親しむという点でも面白い機会ですが、大学や大学院で研究に携わる学生にとっても、新たな視点を培う意味でも意義があると言えるのではないでしょうか。
2023年のイグノーベル賞授賞式は9月14日にWeb開催されます。関心を持った人は今年の受賞者にぜひ注目してみてはいかがでしょうか。
この記事やイグノーベル賞への理解を通して、みなさんの科学や研究への興味に繋がれば幸いです。




