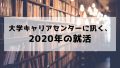「製薬会社の研究職に就きたいけど、難しそう」
「薬学部じゃなくても製薬会社に入れるの?」
このような不安を抱いている、製薬会社志望の就活生も多いでしょう。
一般的に、製薬会社への就職は競争率が高い傾向にあります。しかしながら、自分の専門性をアピールすることで薬学部ではなくても製薬会社に入社するチャンスを得られるものです。
本記事では、製薬会社に興味がある学生向けに、製薬業界の情勢を詳しく解説します。製薬会社の研究職になるために必要なことをはじめ、薬学以外でも製薬会社で活躍できる研究分野、製薬会社の研究職の種類などにも触れます。
この記事を読めば製薬会社への就職を考えるための第一歩になりますので、参考にしてください。
製薬業界の情勢
国内の製薬会社としては、「塩野義製薬」「第一三共」「武田薬品工業」「中外製薬」などが挙げられます。海外では「ファイザー」や「メルク」などの会社が有名です。新型コロナウイルス関連のニュースで耳にしたことがある会社も少なくないでしょう。
日本の医薬品は「医療用医薬品」、「一般用医薬品」、「要指導医薬品」の3つに分類されています。医療用医薬品は病院で医師が患者さんに処方する処方薬のことで、購入には処方箋が必要です。
一般用医薬品と要指導医薬品はいわゆる市販薬で、処方箋がなくても薬局で購入することができるお薬です。さらに、医療用医薬品は、いわゆる新薬と呼ばれる「先発医薬品」と、特許が切れ他のメーカーが製造できるようになった「後発医薬品」(いわゆるジェネリック医薬品)に分けられます。
コロナウイルスのワクチンや治療薬開発でも話題になりましたが、製薬会社の競争は新薬の開発力が鍵を握るとされます。こうした創薬には10年以上の時間と数百から数千億円規模の費用が掛かる一方、成功確率は2万分の1以下と言われています。
これまで生活習慣病関連分野における新薬販売の収益が多くの製薬会社を支えてきましたが、近年ではこれらの特許が切れ、収益が悪化する例も珍しくありません。
このように、重要度を増す創薬分野では、ビッグデータ解析、AI、iPS細胞などといった最新技術を駆使した手法が注目を集めており、創薬系バイオベンチャーと呼ばれる企業も現れています。
創薬業界で高まるデータサイエンティスト需要に関する記事はこちらからご覧いただけます。
他方で、後発医薬品の分野では、「東和薬品」「沢井製薬」「日医工」などが有名です。後発医薬品の市場はここ10年で2倍ほどに成長しており、2024年3月の後発医薬品の使用割合は82.75 %に上ります。更には「ジャパンブランド」を打ち出しての海外展開も期待されています。
参考: 厚生労働省(2021-09-13)「『医薬品産業ビジョン2021』の策定について」
参考: 日本取引所グループ(2022-11)「創薬系バイオベンチャー企業について」
参考:厚生労働省(2025-10-29)「保険者別の後発医薬品の使用割合(令和6年3月診療分)を公表します」
製薬会社の研究者になるために必要なこと
製薬会社の研究者になるためには条件があります。
具体的には、いずれかの条件が求められるケースが一般的です。
- 修士課程を修了していること
- 博士課程を修了していること
- 6年制の薬学部を卒業していること
それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
修士課程修了
製薬会社の研究者になるのであれば、「修士課程」を修了することが最低限条件です。
製薬会社の研究職には、製薬に必要な専門知識や問題を解決するスキルが求められます。
薬学部の授業だけで得られるような、まんべんなく幅広い分野の知識だけでなく、専門的な研究経験も求められます。
そのため、製薬会社に限らず、修士以上の学位を取得していることを研究職の応募条件をとしている企業も少なくありません。
将来製薬会社の研究職に就きたいと考えている場合は、修士課程を修了しておくことが望ましいでしょう。
博士課程修了
化学・薬学系の博士課程修了者であれば、多くの製薬会社の研究職にエントリーできます。
研究に真摯に取り組んでいれば、専門知識と研究スキルが備わっているはずなので、先述の研究職に必要な人材の条件はクリアしていると言えるでしょう。
博士課程での研究は、以下の流れで進めるケースが一般的です。
①研究テーマを決める
②研究計画を立てる
③テーマの解決方法を考える
④実験を行う
⑤結果の考察・レポート作成
⑥次に行うことを決める
企業の研究部門においても、大学の研究室と似たような流れで業務をしているため、博士課程修了者の場合、即戦力として活躍できる可能性があります。
また、海外での学会発表や民間企業との共同研究経験もあれば、なおさら企業が欲しい人材に近づくでしょう。
ただし、博士課程で製薬に関連する研究を行ってきたからといって、必ずしも製薬企業から内定がもらえるわけではありません。
一般的に、企業は自社の利益に貢献できるような人材を求めています。
そのため、面接では自分にどのようなことができるかをしっかりとアピールする必要があります。
インターンシップを通じて実際の業務を経験することで、研究での実績をどのように業務で生かすことができるか、アピールしやすくなるかもしれません。
6年制の薬学部を卒業していること
研究職の場合、学部卒では応募条件を満たしていない事も多いですが、6年制の薬学部に通っていた学生は採用の対象になるケースもあります。
医薬品に関する基礎知識など、薬学部でしか学べないことも多く、この点が薬学部の学生が評価されているポイントです。
研究に対する熱意をアピールして、会社に貢献できることを伝えられれば内定が近づくことでしょう。
ただし、企業が研究職として採用する人材に求めているのは、専門的な知識と、研究プロジェクトを管理し自走できる能力であることも多いです。
そのため、たとえ専門的知識を学べる薬学部出身だとしても、学部のカリキュラムだけでは研究の経験が培われにくく、研究職として採用されるのは厳しいかもしれません。
とはいえ、学部卒で研究職の選考を受けられるのは大きなチャンスです。
応募要件を満たしているのであれば積極的にエントリーしてみましょう。
製薬会社の就職が難しい理由

製薬会社への就職は、学部卒や修士だけでなく、博士ですら難しいのが現実でしょう。
具体的には、次のような理由が挙げられます。
・募集自体が少ない
・専門性だけではなくコミュニケーション能力も求められる
それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
募集自体が少ない
製薬会社には研究職も開発職もありますが、募集自体は決して多くありません。
さらに、人気職であることから応募する学生が多く、競争率が高くなっています。
エントリーの倍率は少なくとも10倍〜100倍と言われており、内定を得るにはその中で勝ち残らなければなりません。
内定をもらうためにも、自分の研究にしっかりと取り組みつつ、インターンの参加や業界研究、企業研究、自己分析などの活動も積極的に行うことが必要でしょう。
専門性だけではなくコミュニケーション能力も必要
研究職に就くには、専門分野に精通することも重要ですが、コミュニケーション能力も必要です。
製薬会社の研究部門では、効率よくスピーディーに新しい薬を開発するためにも、違う分野の研究を行っている人たちや別の部門と連携し合って業務を行います。
そのため、報告・連絡・相談はもちろんのこと、自分の研究を知らない人に対しても、研究内容をわかりやすく説明するためのコミュニケーション能力も必要です。
せっかく研究を行う能力があったとしても、コミュニケーションが苦手であれば、面接で不採用になってしまう恐れもあります。
そのため、もし苦手な場合は、所属している研究室内での活動のような身近なところからコミュニケーションを図るように意識してみましょう。
製薬業界を目指す学生がやっておくべきこと
製薬会社で働くためには、大学の勉強だけではカバーしきれない実践的なスキルを身につけたり、明確な志望動機をアピールしたりなどの準備が必要です。
特に、研究開発職を目指す場合は、大学院での研究経験や専門性の深掘りが求められるほか、インターンシップの参加経験の有無も重要視されます。
ここでは、製薬業界を目指す学生が就職活動に向けてやっておくべきことを詳しく見ていきましょう。
大学院で研究スキルを身につける
製薬会社の研究職を目指す上で、大学院での研究経験は重要なポイントです。
実験計画の立案やデータ解析、論文の執筆・発表などを通して、研究員として必要な論理的思考力や問題解決力、粘り強く取り組む姿勢が養われます。
また、修士課程以上の学位を取得していることが応募条件となっている製薬会社も多いため、早期から「どの研究テーマが製薬業界と関係が深いのか」「企業にどうアピールできるか」といった視点で研究に取り組むことも大切です。共同研究や学会発表を経験しておくと、実績として選考でも有利に働くでしょう。
製薬企業のインターンシップに参加する
製薬会社で実施されるインターンシップは、企業の研究現場や業務内容を実際に体験できるとても貴重な機会です。研究部門のインターンでは、実験補助やディスカッションを通して現場感覚を養えるため、職場の雰囲気や社員の考え方を直に感じられるでしょう。
また、インターンでの活躍が評価されると、本選考で有利に働くケースもあります。一般的に、インターンの募集は夏(6〜8月)と冬(12〜2月)に実施されます。希望者も多いため、なるべく早いタイミングでの情報収集とエントリーが必須です。近年では、オンラインで実施する企業も増えており、自宅や学校にいながら、講義やセミナー、グループワークなどに参加できます。遠方に住んでいる学生が参加できるプログラムも充実しているため、積極的に情報収集をしていきましょう。
選考で評価される志望動機&自己PRを考える
製薬会社の選考では、自己PRや志望動機を通して「企業への貢献意欲」や「専門性の活かし方」、「将来的なビジョン」などが問われます。これまでの研究内容だけでなく、研究で得たスキルや考え方を企業活動にどう応用できるかを伝えることが重要です。
また、企業ごとに研究テーマや社風が異なるため、志望動機は「なぜその企業でなければならないのか」といった深いところまで踏み込むことが重要です。他の志望者との差別化を図るためにも、企業説明会やインターン、OB・OG訪問などに積極的に参加して、ホームページでは得られないリアルな情報に触れることが、説得力のある志望動機や自己PRづくりにつながります。
薬学以外でも製薬会社で活躍できる研究分野
製薬会社では、製薬に関わる専門的な知識と研究スキルがあれば薬学部以外の学生も採用しています。
現在製薬業界では、テクノロジーの進歩や研究の細分化によって、薬学の知識だけで創薬を行うことが困難になっており、各製薬会社でさまざまな専攻の学生を募集しています。具体的は、次のような分野です。
- 生物学
- 分析化学
- その他の製薬に関わりのある専門的な研究分野
それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
生物学
製薬会社では、新薬によって人体へどのような影響があるかを正確に把握することが求められます。そのため、「分子生物学」「生理学」「ゲノム科学」などの生物学分野を専門とする学生は、創薬の根幹を支える存在として注目されているのです。
近年では、遺伝子組換え技術や細胞培養技術を用いた「バイオ医薬品」の開発も進んでおり、生物学系の知識と実験経験がますます重視されています。バイオ医薬品とは、たんぱく質などの高分子を有効成分とする医薬品で、がんや難病の治療にも使われており、今後さらに需要が高くなる分野とされています。
このように、生物学系の研究を行っている修士課程、博士課程の学生は、製薬会社の就職活動において有利になるでしょう。
分析化学
化学を専攻している学生の中でも、特に分析化学を専門とする学生は、製薬会社での活躍が期待されています。
分析化学は、物質の構造や組成、性質を明らかにする学問であり、創薬や製剤のプロセスにおいて欠かせない分野の一つです。
医薬品の原料や有効成分、さらには不純物に至るまで、製薬会社における安全性・有効性の評価には精密な分析が不可欠です。
そのため、化合物の構造解析や新たな分析手法の研究に取り組んでいる大学院生は、製薬企業からも高い関心を寄せられています。
その他の製薬に関わりのある専門的な研究分野
生物学や分析化学に限らず、製薬に応用可能な専門性を持つ分野であれば、研究職としての採用チャンスは十分にあります。例えば、工学部の応用化学、化学工学、応用生物工学といった専攻では、医薬品の合成プロセスやバイオ医薬品の製造技術など、製薬業界に直結する知識を活かせるでしょう。
また、創薬のスピードと効率性が求められる中、ビッグデータ解析やAI創薬などを扱うデータサイエンティストの募集も多くなっています。
そのため、統計解析、機械学習、プログラミングなどに長けた情報系・数理系の学生にもチャンスがあると言えるでしょう。
博士課程修了予定者の就活時期について
企業によっては博士採用枠を設けている場合もあります。
博士課程修了予定者は学士や修士の就活とは違い、「3月に説明会開始、6月に選考開始」というような就活ルールがありません。
そのため、一般的に言われている新卒の就活時期とは異なることが多く、注意が必要です。
できるだけ採用される可能性を上げるためにも早い段階で就活をスタートしておきましょう。
製薬会社の研究職の種類

研究職の中にも種類がいくつかあり、主に基礎研究と応用研究に分類されます。
基礎研究
基礎研究では5〜10年後に必要とされるであろう技術の基盤になるような研究を実施します。基本的にその研究単体では会社の利益にならないものが多いのが特徴です。製薬会社においては、新しい成分の発見や病気の原因解明など、薬を作る前に必要な基礎研究を行っています。また、基礎研究は大学の研究室や公的な研究機関でも実施されます。
基礎研究に興味のある方に、おすすめの職種と言えるでしょう。
応用研究
応用研究とは、基礎研究で得られた結果をどのように活かして利益を生み出すかを発見する研究のことです。製薬会社によって応用研究の定義はさまざまですが、一般的には「探索研究」と「非臨床試験」が応用研究に相当するものだと言われています。
探索研究では、基礎研究から解明されたデータをもとに薬の元素を探す研究を行い、これまで企業が培ってきた技術と基礎研究の結果を組み合わせて化合物の生成を行うことが多いです。
探索研究が終わると、非臨床試験に移行します。非臨床試験とは、生成した化合物の効果や毒性などを調べる試験のことです。動物実験や培養した細胞を使った実験を行って評価します。非臨床試験で問題ないことがわかれば臨床試験へと移れるでしょう。
基礎研究と応用研究の違いについてはこちらの記事もぜひチェックしてみてください。
研究職以外の職種
製薬会社には研究職以外にも、医薬品の開発から販売、規制対応に至るまで幅広い職種が存在します。自分の専門やスキル、さらには理想とする働き方に合った職種を選ぶことで、製薬業界でのキャリアの可能性は大きく広がります。
ここでは、製薬会社への就職を希望する学生に向けて、研究職以外の代表的な職種とその役割について詳しく見ていきましょう。
CRA(臨床開発モニター)
臨床開発職(CRA)とは、医薬品の臨床試験が適切に行われているかを医療機関と連携しながら管理・監督する職種であり、新薬の開発プロセスにおいて極めて重要なポジションです。
治験を実施するための医療機関や担当医師の選定したり、治験実施中にモニタリングをしたり、さらには治験が終了したら、CRFや治験薬を回収したりなどの業務を通して、薬の安全性・有効性を証明する役割を果たしています。
医療系や薬学系、生命科学系などの理系出身者が多い傾向にあるものの、近年では文系出身者が活躍しているケースもあり、コミュニケーション能力や管理能力が重視される職種でもあります。
安全性情報管理(PV・ファーマコヴィジランス)
医薬品は、開発してリリースされてからも、副作用や安全性に関する情報を継続的に監視・評価し続けなければなりません。これらの業務を担うのが「安全性情報管理」、通称 PV(ファーマコヴィジランス) です。
具体的には、医療従事者や患者から寄せられた副作用の情報を収集・解析し、必要に応じて製品の添付文書を改訂したり、厚生労働省へ報告をしたりします。
その他にも、医薬品の添付文書・患者向けパンフレットの改訂や国内外における安全性に関する最新情報の収集と定期報告なども、安全性情報管理の業務です。
法令理解やデータ処理能力、正確な文章力も求められるため、文理問わず幅広い人材が活躍できる分野と言えるでしょう。
営業職(MR)やマーケティング職
製薬会社の営業職は「MR(Medical Representative)」と呼ばれ、医師や薬剤師などの医療従事者に対して、自社製品に関する情報提供・収集を行う専門職です。単なる営業だけではなく、医薬品に関する高度な知識と説明力が求められるため、理系出身者の学生が採用される傾向にあります。
一方、製薬会社におけるマーケティング職では、市場分析や製品戦略の立案、プロモーションの企画実行など、より戦略的な業務を担当します。新薬の発売時には、ターゲットとなる医療分野や患者層を見極めて、競合他社との差別化を図る戦略設計が必要です。
MR・マーケティング職のどちらの職種も、コミュニケーション能力や論理的思考力、業界動向への敏感さが求められる仕事です。研究職とは異なる形で医療に貢献したいと考える方に、最適な仕事と言えるでしょう。
製薬会社の参考年収(五十音順)
製薬会社は一般的に年収が高いといわれていますが、実際のところどれくらいの年収なのでしょうか。
ここでは2022年3月時点で上場している代表的な製薬会社5社の平均年収を紹介します。
アステラス製薬株式会社
およそ1,110万円(平均年齢42.7歳)
参考: アステラス製薬(2024-06-20)「2024年3月期(第19期)有価証券報告書」
エーザイ株式会社
およそ1,054万円(平均年齢44.2歳)
参考:エーザイ株式会社 112期(2024年3月期)有価証券報告書
協和キリン株式会社
およそ994万円(平均年齢43.2歳)
参考:協和キリン株式会社 2024年12月期(第102期)第99期)有価証券報告書
武田薬品工業株式会社
およそ1,081万円(平均年齢43.3歳)
参考:武田薬品工業株式会社 2023年度 (2023年4月1日〜2024年3月31日)第147期有価証券報告書
日本新薬株式会社
およそ784万円(平均年齢41.5歳)
参考:日本新薬株式会社 第161期(2024年3月期)有価証券報告書
有価証券報告書を調べてみると、大手製薬会社の年収は800万弱から1,100万円程度であることが分かりました。ただし、これらの年収は研究職以外の職種の年収も含まれているため、研究職だけの年収の場合は多少変わるかもしれません。
また、国税庁の発表した令和5年の民間給与実態調査によれば、給与所得者全体の平均年収は460万円となっており、製薬会社の年収が高いことがわかります。こうした給与の面での待遇の良さが人気に繋がっていることが考えられます。
参考: 国税庁(2022-09)「令和5年分 民間給与実態統計調査」
まとめ
この記事では、製薬会社の研究職について解説しました。
研究職への就職を希望する大学院生は多いと考えられるため、採用されるためには応募要件や身に着けるべき能力を確認し、就職活動に臨むことが重要です。
また、博士課程修了予定者の場合は選考スケジュールが修士課程修了予定者とは異なる場合があります。
そのため、できるだけ早めに業界研究などの準備をするとよいでしょう。
業界研究の進め方については、こちらの記事をチェックしてください。