近年、大学院博士課程修了者の中で、社会進出する学生の数が増加している一方で、将来のキャリアの選択肢として大学教授の道を志す学生も増えています。
大学で働いている先生は、全員教授というように思っている方もいるかもしれませんが、すべての大学教員が教授という役職に就いているというわけではありません。
まず、大学教員にはどのような役職があるか解説していくとともに、大学教員になるために必要な資質、キャリアパスや給料水準について紹介していきます。
大学院での教育や研究に熱心に取り組んでいる方の中には、将来的には大学教授の道を目指すという夢を抱いている方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、その道は険しいものでもありますが、特定の分野において深く探求したいという熱意があるのであれば、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。
本記事を読んで、大学院生が大学教授のポジションを目指すためには、どのようなルートとなるのかを明確に把握しましょう。
大学教員と大学教授の違いとは?
まず、大学教員と大学教授の違いについてみていきましょう。
「大学における教育職」という仕事を想像すると、多くの類似した職種が存在します。
まず、専任教員と呼ばれる、一般的な企業における正規雇用と同じようなステータスを持つ仕事が3つあります。大学での専任教員として採用されると、多くの場合は最初は「講師」として勤務します。そして、講師は経験と研究を積み重ねることで「准教授」と呼ばれるようになり、さらに研究と経験を積んで「教授」と呼ばれるようになります。
大学教授と大学准教授の区別は大学によって異なりますが、明確な基準が設けられているわけではなく、通常は年功序列の影響を受けて変動します。近年では、いくつかの大学では独自の「評価システム」を導入し、自身の教育と研究に関する目標を設定し、それを数値化して成果として評価し、次の准教授を教授に昇進させる基準としているところもあります。これは一般企業の昇進システムをイメージしてもよいかもしれません。
大学での役職の違いは?
大学教員にも多くの役職があり、講師以外にも講師よりも上の役職として、教授や准教授と呼ばれる役職があります。
さらにこれら以外にも、助手や助教といった役職もあります。まずそれぞれの役職は大学においてどのような立場にあたるのか、もっとも下の役職にあたる助手から順にみていきます。
助手とは
助手とは、学校教育法上 “教授や助教授(現在の准教授)の職務を助ける” 立場であると定められています。
しかしながら、助手の仕事は多岐にわたるのが実情であり
- 講義や演習の準備
- 実験や演習における実演
- 学科における事務
といったような教育研究を補助する立場の助手もいれば、独立した若手研究者として位置付けられている助手もいます。
さらに、大学ごとの制度として大学院博士後期課程の学生が就くポストとして助手という役職が設けられている事例もあります。
助教とは
上述のように、助手と呼ばれる役職は雇用形態により業務内容が大きくことなることが問題となっていました。そこで近年新設されたのが、助教とよばれる役職です。
助教は “自ら教育研究を行うことを主たる職務とする者” と定義されています。
そのため、助教が行うことが想定されている業務としては大学における授業科目の担当
学生への研究指導などが挙げられており、助手との違いとしては授業科目を担当できるといった点になってくると考えられます。
講師とは
大学設置基準上、講師とは教授や助教授(いまの准教授)に準ずる職務に従事することが求められ、 “教授や助教授(いまの准教授)となることができる者” もしくは “大学教育を担当するにふさわしい能力を有する者” が就ける職種とされています。このことから講師には大学における授業科目を担当でき、将来的には准教授や教授になることのできる人材が求められていると考えられます。
さらに講師のなかでも専任講師の場合任期の定めのない職であることが特徴です。一方、上述の助教の多くは任期の定めがある職であることが多く、この点が大きな違いと考えられます。
准教授とは
大学准教授は学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事することが主な職務であるとされています。そしてさらに研鑽を積み、昇進して教授となることが一般的です。
教授とは
大学教授とは、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事することのみでなく、大学や学部全体における教学面の運営についても行うこととされています。そのため、大学における授業科目の担当、学生への研究指導のみでなく大学や学部の運営にも関わっていく役職です。
なお、大学教授に至るまでの一般的なキャリアパスとしては、博士後期課程修了後ポスドク期間を経た後【講師 → 准教授 → 教授】というように昇進していくのが一般的です。
講師と非常勤講師の違いとは

ここまでは、大学教授に至るまでのキャリアパスに含まれる講師を例に解説してきましたが、講師以外にも似た呼称の役職として非常勤講師と呼ばれる役職があります。しかしながらこれらの役職は全く異なるものです。
講師はフルタイムの仕事
まず講師とは、場合によっては専任講師とも呼ばれ、フルタイムの教員となります。多くの講師の場合大学における授業科目の担当のみではなく以下のような業務も担当します。
- 学生の研究指導
- 大学や学部の運営に関わる仕事
このように講師は幅広い業務を行うことになるのが一般的です。
非常勤講師はパートタイムの仕事
一方非常勤講師とはパートタイムの教員であり、一般的に授業の担当数に応じ給料が支払われます。そのため講師(専任講師)とは異なり、大学における授業科目のみを担当します。
講師になるには
どのようにして大学における講師になるのでしょうか。フルタイムの職である講師(専任講師)を例にとって紹介します。
必要な資格
講師として大学で採用されるためには、文部科学省による大学設置基準により定められている資格が必要となります。
一般的には、教授や准教授になるためのキャリアパスである講師は、大学設置基準では教授や准教授になることができる者が講師になれるとされています。
実際に、教授や准教授になるための資格として代表的なものとしては
- 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者
- 研究上の業績が博士の学位に準じると認められるもの
- 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
などが挙げられています。
専門性や実績が必要
講師になるためには専門性や実績が重要視されており、必要な資格でも明らかなように、大学院博士後期課程を修了し博士の学位を取得するか、これに準ずる研究業績が必要になってくるものと考えられます。
また、大学で教育・研究活動を行うにあたっては、学生への研究指導を行う必要があることから、次世代を育成できるだけの専門性がなければ大学講師としては務まらないでしょう。
応募方法
大学の講師は、一般に公募により採用が行われます。この公募の多くは
- JREC-IN
- 学会のホームページ
- 大学のホームページ
に掲載されることが多いです。
また、応募要項にもよりますが
- 業績を証明する書類や主要論文の複写
- これまでの教育歴を証明する書類
- 教育を行うにあたっての抱負をまとめた書類
を専用書式にまとめ、大学や公募担当の部署に書類を送付することで応募できるのが一般的です。
社会人から大学講師になれるのか
専攻分野について、優れた知識及び経験を有する場合、社会人が大学の講師になることも可能でしょう。また、公的研究機関や企業における研究所での成果を論文として学会誌などに公表、この論文をもとに論文博士の学位を取得し、大学の講師として着任した事例も多くみられます。
コネクションがあると有利
また大学の講師になるにあたっては、コネクション、すなわちコネは採用にあたって有利に働きます。講師を採用する際、公募を行いますが知り合いの研究者に公募案内を直接送付するというように、事前に適任者に声をかけていることはよくあることです。このように声をかけてもらったうえで公募に応じた場合、選考において有利であることは間違いないでしょう。
昇進はあるのか
また大学の講師は、特任講師や非常勤講師を除いて、いわゆるパーマネント職(任期の定めのない職)です。そのため着任後、一定の成果(論文数など)をあげるに従い、准教授や教授へと昇進していくのが一般的です。
講師の給料はいくらか
大学の講師の給料はどの程度なのでしょうか。給料は、年齢や雇用形態(常勤(専任)や非常勤など)により大きく変わってきます。
常勤講師の月収
大学における常勤講師の月収は、40万円程度と言われています(手当など含まず)。また所属する大学にもよりますが、この金額に加え通勤手当や所定の講義数を超え講義を担当した場合の手当などが加わった額が給料となります。この数字だけをみると、月収は多いように見えるかもしれませんが
- 常勤講師は40代がもっとも多いこと
- 常勤講師になるまでは、収入が安定しないこと(ポスドク問題)
を含め考慮すると、給料が高額な職とは言えないかもしれません。
参照:学校教員統計調査
非常勤講師月収
非常勤講師の月収は、担当講義数により大きく異なります。また、勤務する大学にもよりますが、非常勤講師の給料は1講義あたり月額数万円程度と言われています。
そのため、非常勤講師のみで生計を立てるためには、複数の大学で非常勤講師の掛け持ちが必要となるでしょう。そのため常勤の講師に比べ、さらに給料の水準は低いのが現実です。
講師に向くのはこんな人
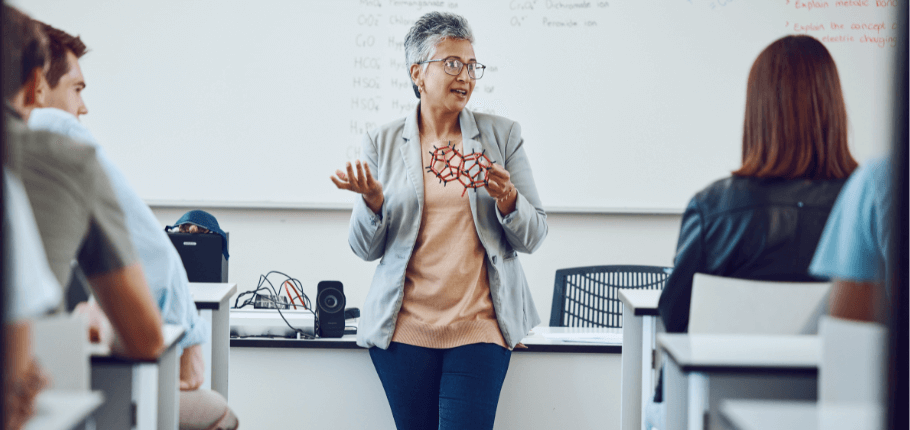
大学における講師は、自分自身の研究を行うのみではなく
- 大学における講義を担当
- 常勤の場合、学部・大学院学生の研究指導
も行う必要があります。
さらに教授へと昇進した場合には
- 大学や学部の運営
にも関わることが求められる人材です。
すなわち、研究者でかつ教育者であることが求められる職となります。
このことから
- 研究を続けたい
- 次世代の人材育成にも携わりたい
という人におすすめの職種と言えるでしょう。
大学教授を目指すには
大学院を修了し、博士号を取得することは、大学教授を目指す一般的なルートです。
大学を卒業した後、修士課程に進んで2年間の前期課程を終え、その後3年間の後期課程を修了することが一般的です。
前期課程では、修士論文の執筆と発表が必要です。
修士号を取得したら後期課程に進み、より高度な研究を行い、博士論文を発表することを目指します。
博士論文が承認されれば、博士号を取得することができます。
一般的には、大学卒業から博士号取得までに最短で5年かかりますが、博士号の取得は非常に困難で、3年間の所定の期間を超えて修了できない場合も少なくありません。
さらに、何年もの月日を費やす必要があるかもしれません。
博士号を取得したら、大学教員に就職することを目指します。
ただし、博士号を持っているだけではすぐに大学教授になれるわけではありません。
さらなる実績を積み上げることや、適切な機会をつかむスキルも重要です。
大学教授になるのは、長い経験の積み重ねが必要で、狭き門であるのは事実ですが、専門性を生かしたやりがいがある仕事です。
まとめ
本記事では、大学教員(大学講師・大学准教授・大学教授)の違い、大学教授になるための一般的なルートについて解説しました。
大学教授になるには、専門分野における卓越した知識や経験が重要です。
大学を卒業した後、修士課程や博士課程に最低でも5年間を費やし、学問の深化を図る必要があります。
それに続いて、研究を継続し、自身の分野で一定の評価を得続けることが求められます。大学教授の道は、長い道のりであり、コツコツと努力を積み重ねる必要があることを理解することが重要です。
社会人から大学教授を目指す場合、企業で研究職に就きながら、じっくりと専門性を高めていくか、再度大学や大学院に入学する必要があります。
大学教授を志す人には、この道を進むために強い意志が求められます。夢を達成するために、決意を持ち続けることがなによりも重要です。
今の研究を続けたい大学院生の方は、ぜひその夢を持ち続けて、「いつか大学教授に」なることを実現してみてはいかがでしょうか。




