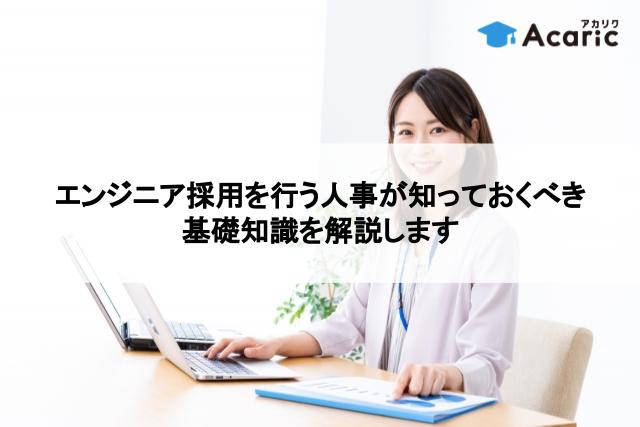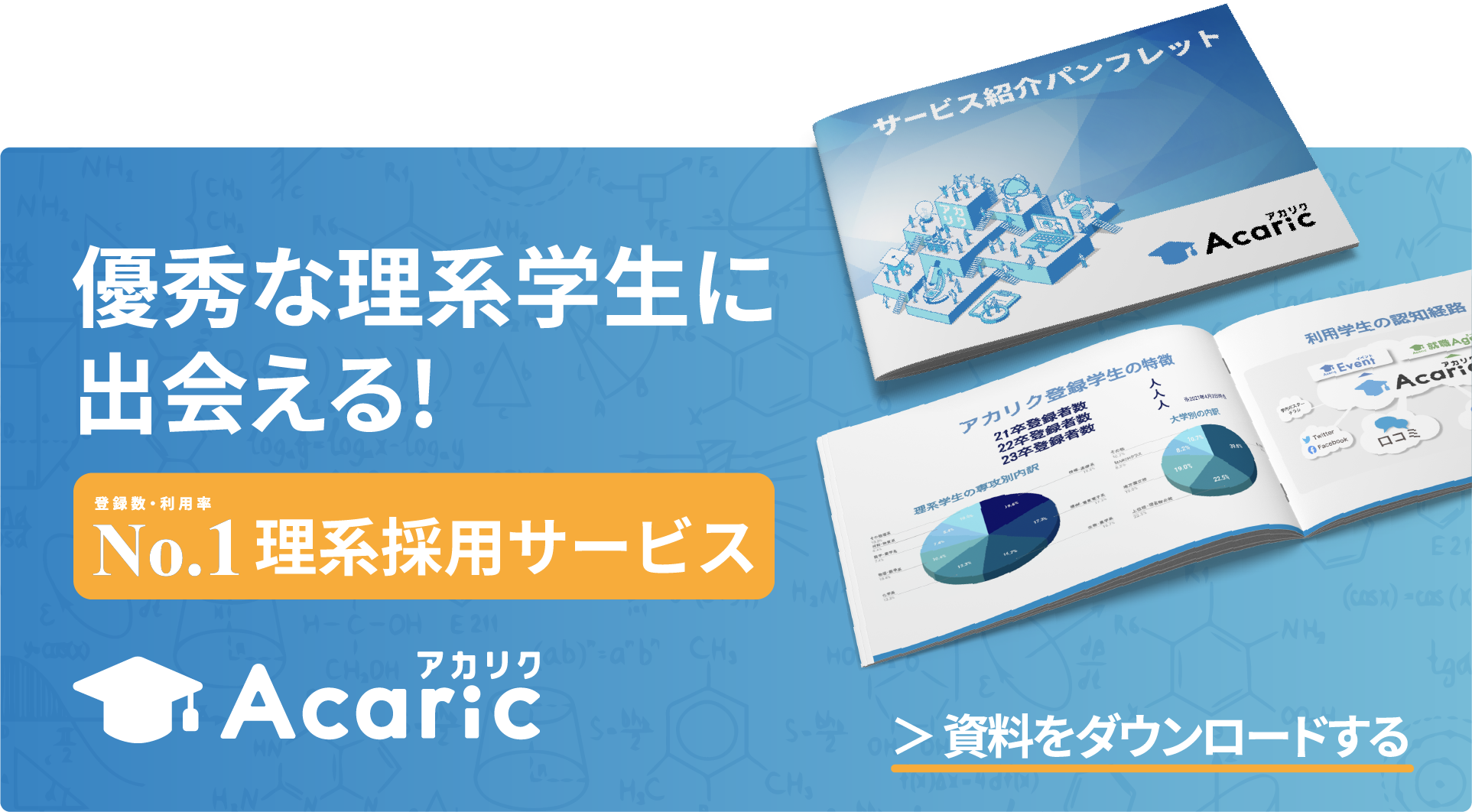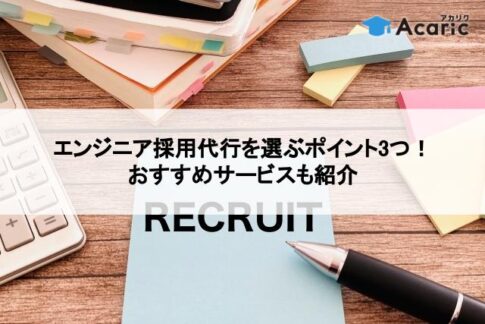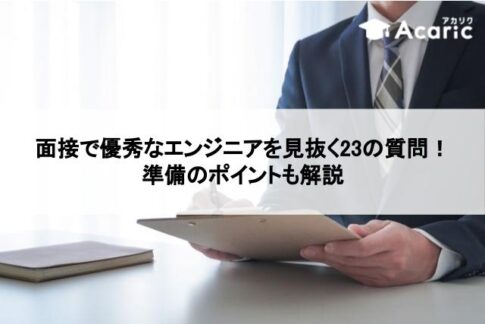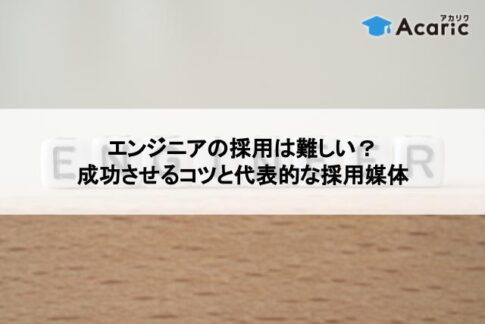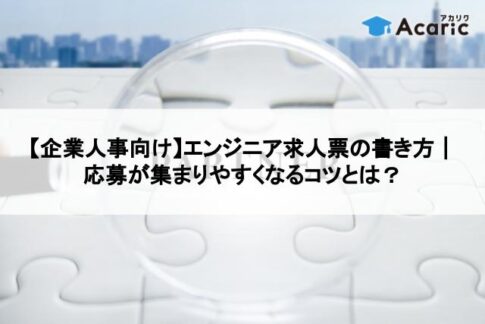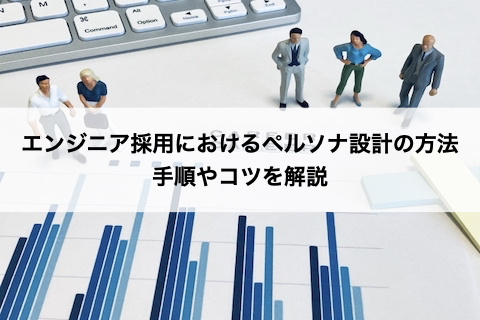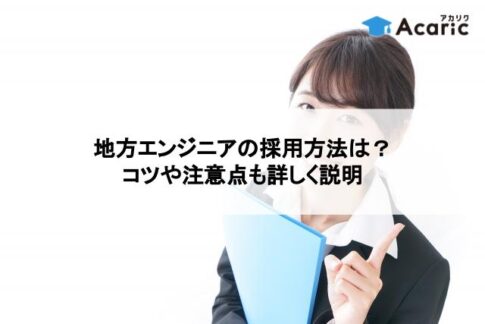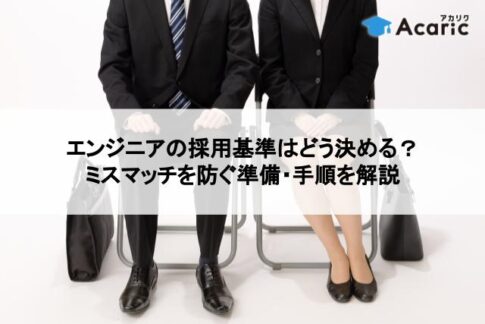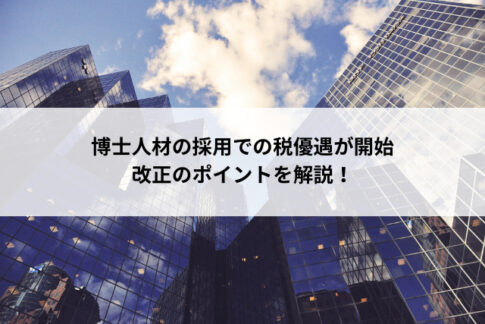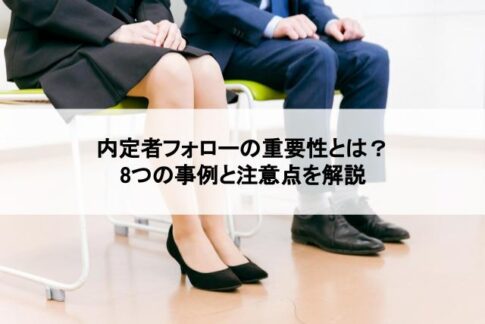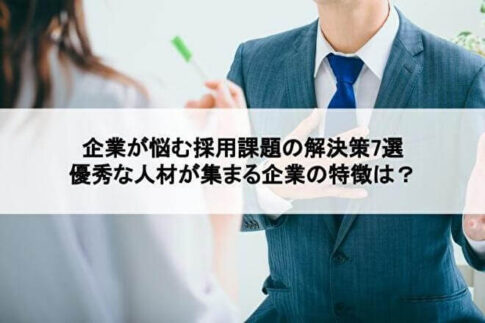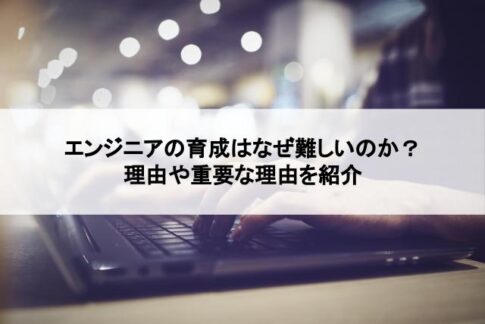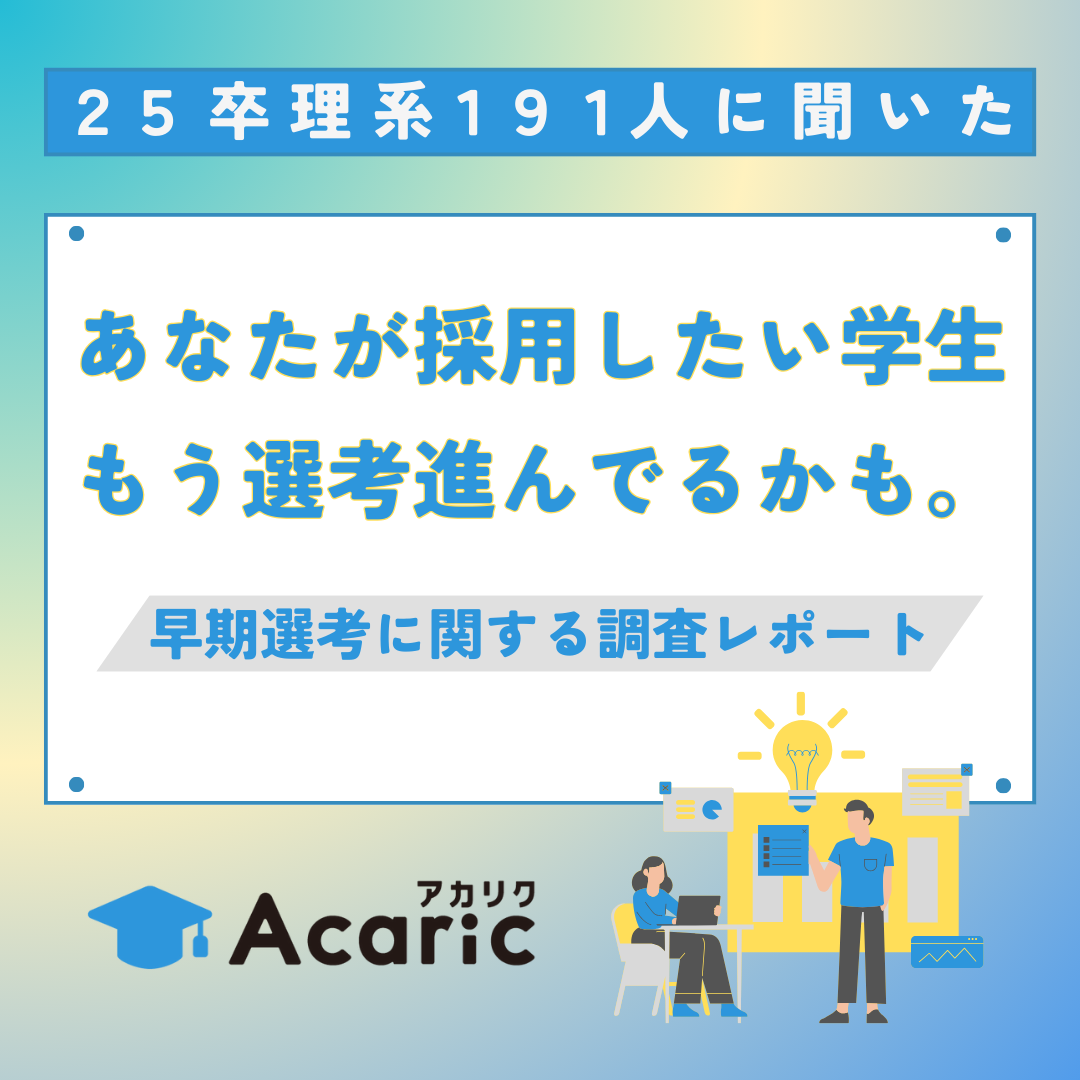エンジニアを採用するにあたって、技術職に関する知識が少なく困ったことはありませんか?
または、応募者とのコミュニケーションが上手くいかず、辞退に繋がっているケースに悩まされていませんか。
求めるエンジニアを採用するには、人事にもエンジニアリングの基礎知識が求められます。
採用が上手くいかないと感じているときは、エンジニアに対する知識不足が原因かもしれません。
この記事では、人事の担当者が知っておくべき知識や、エンジニア採用に役立つ視点についてご紹介します。
目次
近年のエンジニア採用事情で人事が知っておくべきこと

エンジニアを採用するにあたって、人事はどのようなことを知っておくべきでしょうか。
第一には、エンジニアの採用が難航する背景とも言われている「採用市場でのエンジニアリング人材不足」です。
なぜ不足しているのか、不足していることを踏まえてどうすれば良いかを理解できれば、採用においても適切な対策を取れるでしょう。
加えて、エンジニアが求めるものや、エンジニアがどのように転職活動をするかを知ることも大切です。具体的な情報について、下記を参考にしてみましょう。
エンジニア不足が加速している
現代において、IT市場の全体的な成長に加え、各分野でさまざまな技術が常に進歩しています。
AIやロボットといった、新たな先進的ジャンルも注目されるようになりました。
こうした技術への対応力を持ち合わせたエンジニアの採用は、既存サービスの先進化や新たな事業の展開、DXを取り入れた業務改善などに大きく貢献します。
一方で、これらに取り組みたいと思う企業が増えることは、限られたエンジニアの奪い合いを加速させることに繋がるのです。
技術の進歩は今後もさらに進んでいくと考えれば、エンジニアの人手不足はますます深刻化するとも考えられます。
エンジニアがどんな仕事、職場を求めているか
エンジニアにとって、魅力的な仕事や職場とはどのようなものでしょうか。
日経クロステックの「エンジニア転職意識調査」によると、転職理由の上位に占められるのは、「雇用条件」「働き方」「人間関係」「スキルアップ」が多いとわかります。
給与・報酬
まず「雇用条件」に関しては、主に給与のことです。
エンジニアの市場価値が高くなればなるほど、求められる報酬の水準や待遇の条件も引き上がります。
優秀なエンジニアを採用するためには、応募者に寄り添った雇用条件を実現し、他社との競争に勝てる条件を整えることが重要と言えるでしょう。
働き方
「働き方」については、近年でも注目されている「働き方の自由」の尊重が求められます。
人材の多様性を理解し、副業の許可やフレックスタイム制の導入を進めることも一つの方法です。
特にITエンジニアには、リモートワークを希望する人材も少なくありません。
むしろ、パソコン1つでどこでも仕事ができる点から、リモートワークの希望者は必然的に多くなります。
正社員の採用ではなく、フリーランスを業務委託で採用する場合もあるかもしれません。
その場合も、出社の頻度や週あたりの稼働時間などの柔軟な対応ができると、応募者の幅を広げることにも繋がります。
人間関係、スキル、キャリア
「人間関係」と「スキルアップ」に関しては、エンジニアの人柄や求めるスキルと、自社の風土や任せられる業務が必ずしもマッチするとは限らないこともあります。
しかし、「社員同士の連携を強め、オープンでフラットな風通しの良い企業にする」「ギスギスした関係性ではなく、温かく活気のある雰囲気を作る」「社員のスキルアップ意欲に理解を示し、そのための環境を整える」といった工夫があれば、一般的に「働きやすい会社」としてイメージアップに繋がるでしょう。
エンジニアがどんな方法で転職、就職活動をするのか
エンジニアがどのようにして転職・就職活動を進めているのか、最新トレンドや情報をキャッチアップしましょう。
市場にいる人材の動向がわかれば、効率の良いアプローチにも繋がります。
近年では採用媒体に求人を出して応募を待つのではなく、企業側から積極的なオファーをする「ダイレクトリクルーティング」や、SNSを通じた「ソーシャルリクルーディング」など、求人媒体を離れた採用手法も活発化しています。
実際にそのような方法で転職するエンジニアも増えているため、これらの領域をカバーすることは必須と言えるでしょう。
限られた人材の中から応募者を獲得するには、「攻め」の姿勢が求められる場合も多くあります。
媒体に掲載をしながらSNSも積極的に活用したり、求人掲載だけでなくスカウトもできる媒体を選んでみたり、多様なチャネルを駆使すればその分だけリーチを伸ばせます。
データベースに良い人材がいたら、転職を検討していなくてもアタックしてみましょう。
「この会社なら働いてみたい」と思わせられたなら、潜在層にもアプローチできます。
人事がエンジニアに関して身につけておきたい知識

人事がエンジニアを採用するにあたっては、職種・ポジション・プログラミングの基礎知識は覚えておきましょう。
もちろん、プログラミングそのものができる必要はありません。
人事に求められるのは、自社で採用したいエンジニアの募集要項を明確にし、応募者の適性を正しく見極める力です。
エンジニアの職種とポジション
まず、エンジニアには大きく2種類があり、「ITエンジニア」と「ものづくりエンジニア」に分けられます。
前者はIT・Web業界においてシステムの開発や保守・運用を手がける職種です。
後者は建築・化学・素材・工業などの分野において、デジタル機器や機材など、製品の開発に従事しています。
エンジニアの中でも、サービスの設計といった上流工程から、1つ1つのプログラムの制作、完成したサービスのテストや改善など業務の範囲は多岐にわたります。
主な職種とその内容を表にしましたので、参考にしてみてください。
| 職種名 | 業務の内容 |
| システムエンジニア | ITシステムの設計書を作り、チームメンバーに作業を振り分ける。 |
| 社内SE | 自社のシステムの改修や新規導入を担当する。 |
| プログラマー | 設計書に基づいて、プログラムの開発をする。 |
| Webエンジニア | WebサイトやWebサービスのデザインを担当する。 |
| セールスエンジニア | 技術的な専門知識をいかして、システム導入やサービスの提案をする。 |
| フロントエンドエンジニア | Webサービスやアプリにおいて、ユーザーの目に触れる部分(UI)を実装する。 |
| バックエンドエンジニア | Webサービスやアプリを動かすための、裏側の仕組みを開発する。 |
| インフラエンジニア | サービスの土台となる基盤の設計や開発を担う。
配線などのネットワーク環境を構築する。 |
| データサイエンティスト | サービスの開発や改善に役立つ、データの管理や分析を担当する。 |
この他に、特定の領域に特化した「kintoneエンジニア」「Salesforceエンジニア」「モバイルエンジニア」のような職種や、「サーバーエンジニア」「データベースエンジニア」「セキュリティエンジニア」のように専門の分野を担当する職種もあります。
ポジションの種類もさまざまです。
マネジメント層のポジションには「プロジェクトリーダー」や「プロジェクトマネージャー」といった進行管理やチームの統括を担当するポジション、「プロダクトマネージャー(PDM, PdM)」という、市場のニーズ把握やプロダクトの立案など、開発だけでなくビジネスにも大きく関わるもポジションもあります。
さらに、キャリアが上がったエンジニアが挑めるポジションとして、「CTO(最高技術責任者)」や「VPoE(技術部門のマネジメント責任者)」といったものもあるのです。
プログラミング関連の知識
エンジニアを採用するにあたっては、プログラミング関連の知識も必要です。
自社でどのような人材が必要なのか、応募者は何ができる人材なのか、正しく理解するためにある程度の基礎知識は身につけておきましょう。
特にIT業界は技術の進歩するスピードが速いため、常に新しいトレンドや革新があります。
プログラミングをする職種について、主な言語を見てみましょう。
| 職種名 | 主な言語 |
| フロントエンドエンジニア | HTML, CSS, JavaScript, TypeScript,React, Angular, Vue, jQuery |
| バックエンドエンジニア | C, Java, PHP, Ruby, Go, Python,Ruby on Rails, Laravel, CodeIgniter, Symfony |
| インフラエンジニア | AWS, GCP, Microsoft Azure, Docker, Kubernetes |
| データサイエンティスト | SQL, Python,Looker |
| モバイルエンジニア | Kotlin, Java, Swift |
詳しい情報を知るには、社内の既存エンジニアにサポートしてもらうのも一つの手ですが、人事としても正しい知識を持てることは強みです。
応募者の適切な評価にも繋がります。
効率よく優秀なエンジニアを採用するための準備

知識を身につけたところで、次はエンジニア採用のための準備を進めましょう。
主に、募集要項の設定や、入社後のフローや環境の整備が重要です。
市場の状況を踏まえれば、エンジニアの採用は難航する場合も考えられます。
できる限り効率化を図り、優秀なエンジニアとの接点を増やすことが得策です。
社内で必要なエンジニアのリソースを確認
社内で実現したい目標や、解決したい課題をもとに、どれくらいのリソースが必要かを判断しましょう。
リソースによってはフルタイムの正社員である必要がなく、フリーランス人材もターゲットになるかもしれません。
開発チームと密な連携をとり、どのような人材を何名くらい採用したいか、しっかりとすり合わせをしましょう。
必須条件と歓迎条件の策定
入社するエンジニアに何をしてほしいかを考え、「必須条件」と「歓迎条件」をそれぞれ策定しましょう。
「必須条件」が多すぎると、応募のハードルが上がり、候補者が集まらない可能性もあります。
逆に、「必須条件」を妥協しすぎてもミスマッチになりがちです。
どのような条件で採用しているかがはっきりすれば、求職者も自分が応募すべきかどうかを正しく判断できます。
採用後のスキルに合わせた教育体制の構築
同じ求人票で募集をしても、採用した人材のスキルは必ずしも皆同じとは限りません。
その人のスキルに合った教育を提供できるよう、育成の環境を整えましょう。
特に、新卒や若手人材を採用するなら、教育の体制づくりをしておくことは重要です。
先輩エンジニアをOJT担当やメンターにしたり、定期的にフィードバック面談をしたりと、さまざまな方法があります。
採用手法の検討
さまざまな採用の手法から、何を選び、どれくらい注力していくかを決めましょう。
採用手法は、媒体掲載・ダイレクトリクルーティング・人材紹介・リファラル採用・派遣など、実に豊富です。
求める人材や市場の動向に合わせた、適切な戦略作りが重要となります。
求人を掲載しながらスカウトもでき、採用イベントのようなリアルな接点も作れるサービスには、「アカリク」があります。
理系の大学院生やポスドクをメインターゲットにしているため、エンジニアの採用には特に適していることが特徴です。
企業向けサイト:https://biz.acaric.jp/
アカリクサービスサイト:https://acaric.jp/
まとめ:人事がエンジニアを正しく理解できれば、採用効率は高まる

エンジニアに対する理解が深まることで、求人票の質や、採用活動におけるメッセージのやり取り、合否の判断における専門性がアップします。
エンジニアに対する人事の理解度は、応募者であるエンジニアにも伝わるもの。
自分を正しく評価し、求める条件に寄り添ってくれる企業なら、「働きたい」という意欲の向上や動機作りにも繋がります。
もし理系の人材を採用したいと考えていて、院生やポスドクのようなスキルの高い学生を社内のエンジニア候補にしたい場合は、「アカリク」がおすすめです。
無料デモや無料トライアルも可能で、自社に合う人材の検索やお試しのスカウトもできます。
早速始めてみましょう。